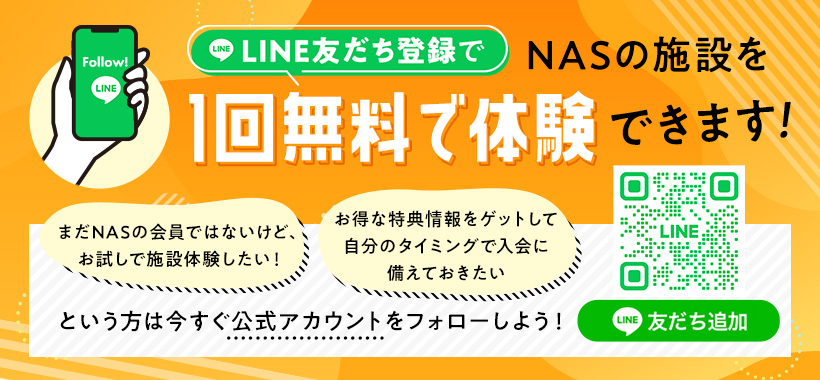食べ過ぎた次の日はどうしたらいい? 対処法の紹介とダイエットに大切な考え方

ダイエットでは常に食事に気をつけ、食べすぎを防ぐことが基本中の基本です。ところがダイエット中であるにもかかわらず、ついつい食べすぎてしまうことも起こりえます。
この記事では、食べすぎた次の日にどうリカバリーしたら良いのか、意識するべきポイントを解説します。食べすぎてしまったからといって、ダイエットを諦める必要はありません。冷静になって、次の日何をすれば良いのか見ていきましょう。ダイエットにはメンタルも大きな影響を与えるので、どのような考え方が必要なのかも取り上げていきます。
目次
Toggle食べすぎた次の日から何をすべき?

食べすぎた翌日、体重の増加や体調の変化に不安を感じる方は少なくないでしょう。しかし、過度に心配する必要はなく、食べすぎたからといって、すぐに体脂肪として蓄積されるわけではありません。人間の体にはホメオスタシス(恒常性)という、一定の状態を保とうとするシステムが備わっています。そのため食べすぎた日があったとしても、いつもの食事に戻れば、急激に太ることはありません。
具体的には、食べすぎた後は2~3日かけて調整することを意識しましょう。食事のバランスは1日単位で厳密に考えるのではなく、数日間のトータルで栄養バランスが整うように意識することが重要です。
食べすぎた翌日に食事を抜くといった極端な食事制限は、かえって体に負担をかけ、体調不良やリバウンドの原因となる可能性があります。必要な栄養素を適切に摂取することが大切です。理想としては、食べすぎた日の翌日は消化に良いものを心がけ、炭水化物(糖質)と脂質を控えめにして、タンパク質を含む食材を積極的に摂るのが望ましいと言えます。
ただし、ダイエット中は糖質を完全に抜くのではなく、質の良い糖質を少量取るようにしましょう。質の良い糖質とは、玄米や雑穀米、全粒穀物などのGI(グリセミック・インデックス)値の低い食物です。GI(グリセミック・インデックス)とは、ある食品を食べたときに、血糖値がどれくらいの速さで上昇するかを示す指標です。数値が高いほど、血糖値が急激に上がりやすく、インスリンの分泌も増える傾向があります。
GI値の低い食品は血糖値の上昇が緩やかなため、インスリンの分泌を穏やかにします。
特に「糖質を取りすぎた」と気にしている方は、以下の記事も併せて参考にしてください。
食べすぎた次の日には何が起こる?
ダイエット中に食べすぎてしまったとしても、次の日体に起こる現象を知っていれば冷静に対処ができます。体の中で何が起こっているのか見ていきましょう。
食べすぎた次の日に太ることはない
ダイエット中でも、断れない飲み会や食事の約束などはあるものです。アルコールが入ると気が緩んで、つい食べすぎてしまうことも。しかし食べすぎても次の日に太ることはありません。大切なのは食べすぎた翌日に何をするかです。
食事をすると体の中では消化活動が行われ、必要な栄養素を吸収したら不要なものを排泄します。食事から吸収した栄養素はエネルギーとして使われますが、消費されなかった分の栄養素が体脂肪となって蓄積されます。
この仕組みから、食べすぎた翌日に脂肪が即座に増えることはありません。
食べすぎた翌日の朝、実際に体重計に乗ると体重が増えていることがあります。この体重増加は、昨夜の食べ物がまだ胃に残っていたり、水分が増えていたりするためです。
食べたものが便となって排出されるのは、食べた後24~48時間後といわれています。(※)つまり、体に脂肪がついたことによる体重増加ではないので、必要以上に落ち込まないでください。
体脂肪1kg増えるのに必要なカロリー

ダイエット中は毎日のように体重計に乗り、数百グラムの体重増減に一喜一憂してしまいます。それでは、1kg体脂肪が増えるのにどのくらいのカロリーが必要かご存知でしょうか。
体内に脂肪として蓄積される際の効率は個人差がありますが、一般的に、体脂肪が1kg増えるには7,200kcalが必要とされています(※1)。
- 体脂肪1kg=脂肪800g+水分200g
- 脂肪1g当たりのエネルギー量:9kcal/g
- 脂肪800g=800(g)×9(kcal/g)=7200kcal
- 体脂肪1kg=7200kcal
もちろん、すべての余剰カロリーが体脂肪になるわけではありません。また、7,200kcalものエネルギー量の食事を1回で、または1日で取ることはほぼあり得ません。
なぜなら1日の推定エネルギー必要量は、身体活動レベルが「ふつう」の成人男性で2,600~2,700kcal程度、成人女性では1,950~2,000kcal程度とされ、7,200kcalは成人男性でも2.5日分、女性なら3日分以上の摂取カロリーとなるためです(※2)。
そのため少々食べすぎたからといってすぐに体脂肪が増えることはなく、また、摂取したカロリーのすべてが体脂肪に変換されるわけではありません。脂肪合成の効率や代謝の個人差も影響するため、一時的なエネルギー摂取量の過多には冷静に対応することが大切です。
この事実は逆の見方をすれば、ダイエットがいかに大変かということが分かります。1kgの体脂肪を減らすためには、7,200kcal分のエネルギーを消費する必要があります。ダイエットは一朝一夕で実現できないと言えるでしょう。
(※1) 出典:東京都福祉保健局「エネルギー消費とウォーキング時間の関係」
(※2) 出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
大切なのは自分を責めないこと
ここまで見てきたように、たった1回または1日の食べすぎでは即太ることはありません。大切なのは、「ダイエット中なのに食べすぎてしまった。今までの苦労が水の泡になった」と罪悪感にさいなまれたり、自分を責めたりしないことです。
ダイエットの成功には食欲をうまくコントロールすることが重要で、そのためにはメンタルの状態が大きく影響してきます。
食べることに罪悪感を覚えたり、食べすぎたからといって自分を責めたりしていると、それがストレスとなりかえって暴飲暴食を招いてしまいます。そうなると負のループに突入し、毎日のように暴飲暴食をしてリバウンドしてしまうことにもつながりかねません。
食べすぎても翌日の過ごし方でリカバリーは可能なため、自分を責めず冷静に対処しましょう。
食べすぎた次の日から行うと良いこと10選

食べすぎた次の日に、すぐに太ることはありません。しかし、脂肪となって蓄積してしまう前に行うべきことはいくつかあります。ここでは、食べすぎた次の日に何を行えば良いのか、具体的に見ていきましょう。対処法を知っていることで、食べすぎたことへの罪悪感も減ります。
控えめでも朝食は取る
食べすぎた翌日、胃もたれなどで食欲がないと感じるかもしれませんが、朝食を少しでも摂ることは大切です。朝食を抜くと、午前中の活動に必要なエネルギーが不足し、集中力の低下や倦怠感につながる可能性があります。また、昼食時に血糖値が急上昇しやすくなり、体に負担をかけることにもなります。
果物は、ビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含み、消化も良い食品です。特にバナナは、カリウムを含んでおり、余分な水分を排出する効果も期待できます。
消化の良い食べ物を取る
食べすぎるときは、外食などで油っこいものや味の濃いものを食べていることが多いものです。しかも量が普段より多いので消化に忙しく、胃腸も疲れています。そのため食べすぎた翌日はできるだけ胃腸に負担のかからない、消化の良い食べ物を取りましょう。
具体的なメニューの例は以下の通りです。
- おかゆ、うどん、にゅうめん
- 豆腐、納豆(※1)
- 白菜(※2)、大根(※3)、キャベツ(※4)
- 鶏むね肉、白身魚、鮭(※5)
- 卵(※6)、牛乳(※7)、チーズ(※8)
- バナナ(※9)、りんご(※9)
※1:納豆は、発酵食品であり腸内環境を整える働きがあります。ただし、ネバネバ成分や発酵臭があるため、胃腸が弱っているときに負担になるリスクはゼロではありません。普段から食べ慣れている方であれば問題ありませんが、調子が悪いときには様子を見ながら少量ずつ摂ると安心です。
※2:白菜は水分が多く、加熱することで非常に消化に良い野菜になります。胃腸への刺激が少なく、体調が優れない時にも適しています。
※3:大根も消化に良い野菜で、特に煮物やすりおろしなどにすると胃腸への負担が軽減されます。大根には消化酵素(アミラーゼ)が含まれており、胃の働きを助ける作用も期待できます。
※4:キャベツは、ビタミンU(キャベジン)を含み、胃粘膜の保護に良いとされます。ただし、生のままだと不溶性食物繊維が多く、胃が弱っている時にはやや負担になることがあります。茹でたり蒸したりして加熱すると、柔らかくなり消化が良くなります。
※5:鮭は、やや脂が多めではありますが、消化の良い良質な脂(不飽和脂肪酸)を含んでいます。焼く・蒸すなどあっさりした調理法であれば、消化に大きな問題はありません。
※6:卵は、特に半熟や温泉卵のように加熱が控えめな状態では、消化が良く胃腸への負担も少ない食材です。ただし、油を多く使ったり、焼きすぎたりすると消化しづらくなるため注意しましょう。
※7:牛乳は、乳糖を分解できる方にとっては消化に良い食材です。ただし、体質によって乳糖をうまく分解できない方の場合、お腹が緩くなるケースもあります。その場合、温めて飲むか、乳糖を除去した製品に切り替える等、無理に飲むのは控えましょう。
※8:チーズ類は種類により消化しやすさに差がある食材ですが、カッテージチーズやモッツァレラなど、水分が多く脂肪が少ないものは比較的消化が良いとされています。
※9:果物の中でもバナナやりんごは消化しやすい食材ですが、特にバナナは熟している方がより消化に良く、りんごは皮をむくことで胃への負担をさらに軽減できます。
一方で、油っこいものや刺激の強い食べ物は消化器官への負担が大きいため、胃腸が弱っているときは避けるのが無難です。
食物繊維を積極的に摂取する
食物繊維は、消化器官の働きを整え、体の状態をリセットするのに役立つ栄養素です。大腸内で発酵・分解されることでビフィズス菌をはじめとした腸内細菌の餌になるため、腸内環境を改善する効果があるとされます。
食物繊維の中でも特に不溶性食物繊維は、腸内で水分を吸収して膨らみ、便のかさを増やすことで腸の蠕動運動を促進します。蠕動運動が活発になることで、便通が促され、体内の老廃物や不要物の排出を助ける効果が期待できます。
食物繊維を多く含む定番の食べ物と、メニュー例は以下の通りです。
- 玄米(玄米ご飯、玄米おにぎり)
- 全粒粉パン(全粒粉トースト、全粒粉サンドイッチ)
- オートミール(オートミール粥、オーバーナイトオーツ)
- ごぼう(きんぴらごぼう、ごぼうサラダ)
- 人参(人参サラダ、人参とツナの和え物)
- キャベツ(コールスローサラダ、キャベツとベーコンの炒め物)
ただし、食物繊維は人間の消化酵素では分解することができないため、胃腸に不調を感じているときは負担が大きくなる可能性があります。そうしたときは避けるのが無難でしょう。
カリウムを積極的に摂取する
食べすぎた翌日は、塩分の摂りすぎによって体内のナトリウム濃度が高くなっている可能性があります。カリウムは、体内の余分なナトリウムを排出し、水分バランスを調整する働きがあるため、食べすぎによって起こりやすいむくみの解消に役立ちます。
カリウムを多く含む定番の食べ物と、メニュー例は以下の通りです。
- ほうれん草(ほうれん草のおひたし、ほうれん草のお味噌汁)
- じゃがいも(肉じゃが、ポテトサラダ)
- 里芋(煮っころがし、里芋のお味噌汁)
- かぼちゃ(煮物、かぼちゃサラダ)
- バナナ・アボカド・キウイフルーツ
- 納豆(納豆ご飯、納豆のお味噌汁)
水分を多めに摂取する
飲み会や食事会などのメニューは塩分が多めで、食べすぎると翌日むくむことがあります。またアルコールを一緒に摂取している場合には、脱水症状を招くことがあるため、アルコールを飲んだのであれば特に水分を多めに摂ってください。
水分の摂り方としては、1度にたくさん飲むのではなくこまめに飲むことが大切です。できれば冷たい水ではなく、常温か白湯にしましょう。
特におすすめなのは白湯です。白湯は体を内側から温めやすく、リラックス効果が得やすいほか、代謝を助ける力にも期待できます。体内の老廃物も排出されやすくなるため、血流の良くなる白湯を飲むことをおすすめします。
アルコールを大量に摂取している場合は、喉が渇いて炭酸飲料やスポーツドリンクなどを飲みたくなりますが、糖分が入っているので食べすぎた翌日は控えましょう。喉の渇きに対しても、白湯を少しずつ飲むことが効果的です。
軽めの有酸素運動をする

食べすぎた翌日は消化を助けたり代謝を高めたりするために、軽めの運動をしましょう。
食べすぎた翌日は普段より疲労を感じているので、いきなり高い強度の運動は体に負担がかかってしまいます。軽く汗ばむ程度の軽めの運動がおすすめです。
食べすぎた翌日にエネルギーを消費するために、軽めの有酸素運動に取り組むことは効果的です。有酸素運動は体脂肪をエネルギー源とする活動なので、脂肪を効率的に燃焼させることができます。また、血流が良くなることで新鮮な酸素や栄養が全身に行きわたり、汗とともに老廃物を排出する助けにもなります。
普段運動をあまりしない方や運動が苦手な方でも、ウォーキングやお散歩ならすぐに行えて気分転換にもなるため、気軽に取り組めます。
また、日常生活の中にも運動を取り入れることができます。例えばエレベーターを使うところを階段に変えたり、徒歩や自転車で移動したりすることも運動につながるでしょう。
ストレッチをする
ストレッチは筋肉の柔軟性を向上させ血流を良くすることで、疲労回復や身体のリラックスに役立ちます。食べすぎた翌日は、消化活動が活発になり体に負担をかけているため、ストレッチを行うことでリフレッシュすることができます。
食べすぎた後のストレッチは身体を緩めるだけでなく、胃腸の働きをサポートする助けにもなります。消化を促進するために軽い有酸素運動と組み合わせると、より効果的なリカバリーが期待できます。
マッサージをする
食べすぎた翌日は体がむくんでしまい、気だるさや不快感を覚えることがあります。特にアルコールが入っていると、水分を取りすぎて体内の水分量が増え、むくみやすくなります。余分な水分や老廃物を排出するために、ふくらはぎや足の裏、リンパのマッサージを行うと良いでしょう。
早めに就寝する

飲み会などで食べすぎた日は夜更かししている場合もあるかもしれませんが、翌日は早めに就寝しましょう。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や産生、記憶の整理などを行っています。また成長ホルモンには筋肉や骨、皮膚を強くし、脂肪を分解してくれる働きがあります。
食べすぎた翌日にはいつもより早くベッドに入り、良質の睡眠が取れるよう工夫しましょう。例えば就寝の3時間以上前には軽めの夕食を済ませ、1時間半前にはお風呂に入り、その後はパソコンやスマートフォンを見ないようにするだけでも、睡眠の質は変わります。
ダイエット中であれば、食べすぎた翌日だけではなく通常の生活でも良い睡眠を取ることを心がけ、心身のバランスを整えましょう。
食べすぎた次の日の食事メニュー例
食べすぎた次の日は、乱れた体のバランスを整えるためにも、食事メニューで調整することがおすすめです。以下では、食べすぎた次の日におすすめの食事メニュー例を紹介します。
【朝食】果物・野菜・乳製品
果物や野菜の中でも、バナナや熟した果物は、消化酵素も含まれているため、消化を助ける効果も期待できます。果物や野菜は、ビタミンC、ビタミンA、カリウムなど、さまざまなビタミンやミネラルを豊富に含んでいます。ただし、ゴボウなどの不溶性食物繊維が多い野菜は胃腸に負担がかかりやすいので控えめにしたほうがよいでしょう。
ヨーグルトなどの乳製品は、タンパク質やカルシウムを豊富に含んでいます。タンパク質は、体の組織を修復するのに必要な栄養素であり、カルシウムは、骨や歯の健康を維持するのに役立ちます。
具体的なメニュー例としては、バナナヨーグルトやスムージーなどが挙げられます。特にスムージーは、複数の果物や野菜を組み合わせることで、さまざまなビタミンやミネラルをバランス良く摂取できます。牛乳や豆乳を加えることで、タンパク質も補給することが可能です。
【昼食】お粥や麺類・スープ
食べすぎた翌日の昼食は、朝食と同様に胃腸に優しく、消化の良いものを選ぶことが大切です。
例えば、お粥は水分が多く、柔らかいため、消化に良い食べ物です。麺類も、うどんやそうめんなど、柔らかく煮込んだものは消化しやすい傾向があります。スープは、食材が煮込まれて柔らかくなっているため、胃に強い負担をかけません。野菜リゾットなど、玉ねぎ・人参・きのこなどの野菜を使ったメニューにすれば、ビタミンやミネラルも補給できます。
揚げ物や油を多く使った調理法は避け、茹でる・煮る・蒸すなどの調理法を選ぶようにしましょう。
【夕食】主菜と副菜の揃った定食
夕食後は活動量が少なくなるため、消化に時間のかかる脂っこいものは避け、良質なタンパク質を中心に、ビタミンやミネラルを豊富に含む野菜を組み合わせた定食スタイルがおすすめです。主菜でタンパク質を、副菜でビタミン・ミネラルをバランス良く摂取しましょう。
具体的なメニュー例としては、以下の通りです。
主菜(タンパク質源)
鶏むね肉の蒸し料理、白身魚の煮付け、豆腐とひき肉のあんかけ…など
副菜(野菜中心)
ほうれん草のおひたし、きんぴらごぼう、ひじきの煮物、温野菜サラダ、お味噌汁…など
鶏むね肉は高タンパク・低脂肪で、消化しやすい食材です。蒸すことで油を使わず、さらにヘルシーに仕上がります。サラダを食べるなら、ブロッコリー・カリフラワー・人参など、お好みの野菜を蒸したり茹でたりして、温野菜サラダとして食べるとよいでしょう。生野菜と比べて消化器官を冷やさず、胃腸への負担が小さくなるとされます。
ただし、ごぼうなど不溶性食物繊維が豊富な食材は、胃腸の調子が良くないときは控えましょう。
タンパク質が多い食べ物については以下の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
食べすぎた次の日に水だけの断食・絶食はNG?
食べすぎた翌日に水だけの断食・絶食を行うことは、確かに短期的には体重減少や消化器官のリセットにつながるように感じるかもしれません。しかし、実際には体への負担が大きく、特に栄養状態や体調によっては逆効果となることもあるため、安易にはおすすめできません。ファスティング(決まった期間の断食・食事制限)に関心がある場合は、医療従事者や専門家の指導のもと実施しましょう。
水だけの断食をすると、必要な栄養素を摂取できないため、体がエネルギー不足の状態に陥ります。すると、体は筋肉を分解してエネルギーを作り出そうとするため、筋肉量の減少につながる可能性があります。筋肉は基礎代謝を維持するために重要な組織なので、筋肉量が減ると基礎代謝も低下し、結果的に太りやすい体質になってしまうことも考えられます。
また、水だけの断食では、ビタミンやミネラルなどの微量栄養素も不足します。これらの栄養素は、体のさまざまな機能を正常に保つために不可欠であり、不足すると体調不良や免疫力の低下などを引き起こす可能性があります。
食べすぎが続く場合の対処法
食べすぎが突発的な飲み会などであれば問題ありませんが、毎日のように食べすぎるのであれば健康上悪影響が出る可能性があります。食べすぎが続くようなら、以下のようなことに気をつけましょう。
しっかり噛んで腹8分目を心がける
よく噛むことは、単に食べ物を細かくするだけでなく、満腹中枢を刺激し、食べすぎを防ぎます。食事を始めると、口にした食べ物は胃に運ばれ、消化が始まります。この過程で、脳の満腹中枢が刺激され、「満腹」という信号が送られるメカニズムです。しかし、この信号が伝わるまでにはある程度の時間が必要となります。早食いの人は、この信号が伝わる前に大量の食べ物を摂取してしまうため、満腹感を感じる前に、食べすぎてしまう傾向があります。よく噛んでゆっくりと食事をすることで、満腹中枢が十分に刺激され、少ない量でも満腹感を得やすくなるでしょう。
また、満腹まで食べてしまうと、胃腸に大きな負担がかかり、消化不良や胃もたれの原因になります。腹八分目に抑えることで、胃腸の負担を軽減し、消化をスムーズに行うことができ、体への負担を減らすことが可能です。
ストレスを軽減させる
食欲がどうしても抑えられないという場合は、ストレスが関係している可能性が高いでしょう。食欲は自律神経と数種類のホルモンによってコントロールされていますが、ストレスがたまると自律神経のバランスが崩れ、よく眠れなかったり食欲をコントロールするホルモンのバランスが崩れたりします。
食欲が満たされると、脳はドーパミンというホルモンを分泌します。ドーパミンとは喜びや快楽を感じるホルモンのため、ストレスがたまっていると過食して快楽を得ようとします。
またストレスによって幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが不足します。脳に糖分が届くとセロトニンが分泌される仕組みなので、ストレス時に甘いものが欲しくなるのはそのためです。
さらにストレスに対応するためコルチゾールというホルモンが分泌されると、血圧の上昇、LDL(悪玉)コレステロールの増加といった健康上のリスクも高まります。
ダイエットによってストレスがたまり、かえって暴飲暴食を招いているのであれば、ダイエットの方法を見直して、上手にストレスを発散させる必要があるでしょう。
睡眠不足を解消する
食べすぎと睡眠不足は深く関わっています。実際に寝不足が続いて体重が増えた経験がある人も多いのではないでしょうか。
アメリカのコロンビア大学が2005年に発表した、肥満と睡眠の研究では、平均睡眠時間が7~9時間のグループと、睡眠時間6時間、5時間、4時間以下に分けて肥満になる確率を調べました。すると、睡眠時間7~9時間のグループに対し、6時間で23%、5時間で50%、4時間以下では73%の肥満になる確率が高くなったという結果が出ました。
睡眠不足になるとグレリンという食欲増進ホルモンが分泌され、レプチンという食欲を抑制するホルモンが減少することが分かっています。
このことから、睡眠不足になると食欲が増進してしまうことになり、肥満になる可能性が高くなることが分かります。
さらに睡眠不足の際に食べたくなるのは、糖質や脂質の多いジャンクフードなどで、いつもより判断能力も低下しているため食べすぎてしまいます。
食べすぎを防止するためには睡眠不足を解消し、良質な睡眠がとれるよう工夫する必要があります。
栄養バランスを見直す
しっかり食事をしているつもりでも、栄養不足に陥っていることが多いのが現代人です。生命活動に必要な栄養素が足りていないことが、食べすぎの原因となっていることがあります。
ダイエットのために極端な糖質制限をしたり特定のものしか食べなかったりすると、栄養バランスが崩れてしまいます。量は足りているはずなのについ食べすぎてしまうという場合は、普段の食事の栄養バランスを見直してみましょう。
炭水化物(糖質)・脂質・タンパク質の三大栄養素とビタミン・ミネラルをバランス良く取ることが大切です。
ホルモンバランスの影響を疑う
女性の場合、生理前になると食欲が増して暴飲暴食をしてしまうという人も多いでしょう。それは生理前にはプロゲステロン(黄体ホルモン)が増えることが原因とされます。
プロゲステロンは妊娠しやすい体にするための女性ホルモンなので、水分や糖分、脂肪などの栄養素を貯めようとします。そのため自分の意思とは無関係に、何か食べたい、食べても満足感がないという状態となり、食べすぎてしまいます。
またプロゲステロンはPMS(月経前症候群)特有のイライラを引き起こします。食べすぎてしまった自分にイライラし、自己嫌悪に陥りやすくなるのもこのためです。暴飲暴食をしてしまうのがいつも生理前である場合には、ホルモンバランスの影響を疑ってみましょう。
まとめ

食べすぎてしまうことは誰にでもあることです。たった1回、または1日の食べすぎで落ち込む必要はありません。食べすぎたら、翌日の過ごし方で十分にリカバリーできるので、心を落ち着けて食事管理と運動を続けましょう。
さらに効果的なダイエットを行いたい場合には、スポーツジムへ通って食事指導を受けるのも1つの方法です。気になる方は、ぜひスポーツクラブNASの店舗へお問合せください。
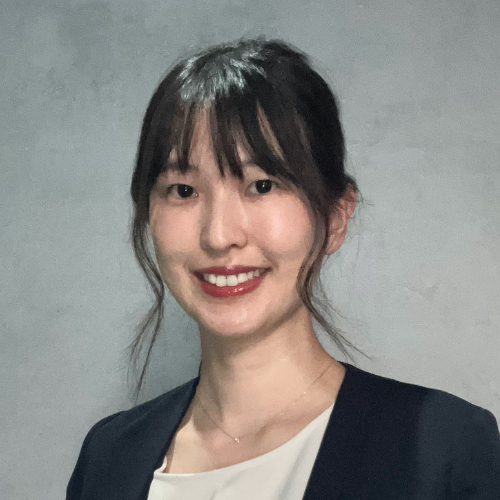
監修者情報
浅香 詩歩スポーツクラブ NAS 株式会社 管理栄養士
大学で栄養学を学び管理栄養士の資格を取得。
スポーツクラブ NAS で栄養指導や、社内情報誌等の監修を行い、採用やスタッフ研修、宣伝業務等、店舗の運営全般に携わっている。
関連記事Related Articles

二の腕をスリムにする方法とは? ダイエットと筋トレで美しいラインを実現
夏が近づくと薄着になるため、二の腕のたるみが気になり始めます。自信を持ってノースリーブやタンクトップを着こなすために、コンプレックスは解消し...
ダイエット 筋トレ・ジム
太りにくい健康的な体になる! 代謝量を上げる10の方法を紹介
太りにくい体を作るには、代謝量を上げる必要があるとよく耳にしますが、そもそも、「代謝」とは一体何なのでしょうか。この記事では代謝とは何かをひ...
栄養・食事 筋トレ・ジム
二の腕痩せに効果的な方法とは? 代表的なエクササイズを紹介 おすすめエクササイズ3選を解説
二の腕のたるみを気にする人は多いです。ダイエットやトレーニングをがんばっても、二の腕痩せの効果をなかなか実感できない人も多いかもしれません。...
ダイエット 筋トレ・ジム
これだけある水泳ダイエットの魅力! そのメリットと注意点を解説
「水泳はダイエットに向いている」と聞いたことのある人は少なくないでしょう。しかし、具体的にどのような側面がダイエットに役立つのか、どうやって...
ダイエット
タンパク質不足が招く影響とは? 健康的で筋肉質な体にタンパク質は必須
私たちは毎日の食事から栄養素を取っていますが、その中でもタンパク質が重要であることはよく知られています。では、タンパク質が不足するとどのよう...
栄養・食事
ジムで足痩せを目指すには?トレーニングの頻度やメニューを解説
ジムでの足痩せを目指すなら、正しいトレーニング方法と継続が重要です。ダイエットは結果が出るまでに1~3か月程度かかることが多いため、無理なく...
ダイエット 筋トレ・ジム
体力をつける方法とは?健康的な未来のための総合アプローチを解説
「体力づくりは大切」と分かっていても、何から始めたらよいのか分からない人は多くいます。 この記事では体力の定義から、体力をつけるための運動、...
栄養・食事
太もも痩せをするには?エクササイズやマッサージの方法を詳しく解説
太ももの太さや太もものたるみが気になっている人は多いものの、どうにかしたいけれどなかなか細くならないのが太ももの特徴です。 当記事では太もも...
ダイエット