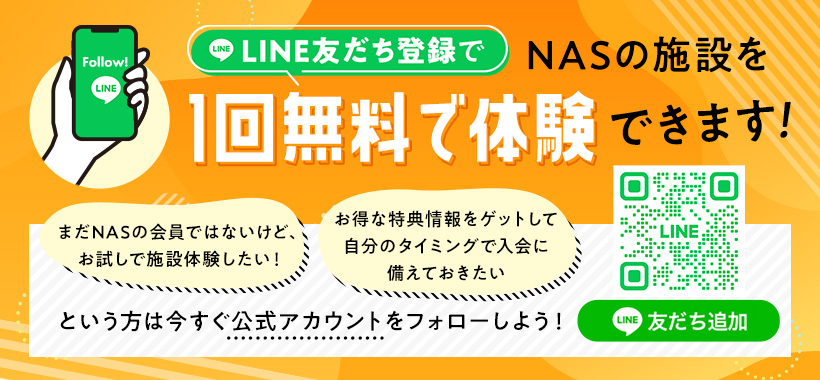背中の筋肉を鍛えるメリットとは? おすすめのエクササイズ3選

背中の筋肉を鍛えたいと思って実践していても、どうもうまくいかないと感じている方もいるかもしれません。背中の筋肉は、どうすれば効果的に鍛えられるのでしょうか。この記事では背中の筋肉の仕組みから、鍛えるメリット、鍛えにくい理由、おすすめのトレーニング種目を解説します。
背中の筋肉を上手に鍛えて、かっこいい背中、しなやかな背中を手に入れましょう。
目次
Toggle背中にある主な筋肉
背中にある主な筋肉の名前と役割を解説します。
僧帽筋
首から肩、背中にかけて広がる大きな筋肉が僧帽筋(そうぼうきん)です。上部・中部・下部に分けられます。肩甲骨を動かしたり、安定させたりする役割や、首をすくめる働きもあります。
僧帽筋上部は、肩を上げて首をすくめるときに働く筋肉です。中部は肩甲骨を内側に寄せるときに働き、下部は肩甲骨の下部を内側に寄せるときに働きます。僧帽筋上部を肥大させると首の横にボリュームが生まれ、中部と下部を肥大させると肩甲骨の間にボリュームが生まれます。
また運動不足などで硬くなると、肩こりの原因になる筋肉です。肩こりに悩んでいる人は僧帽筋を動かすことで、肩こりが改善する可能性があります。
広背筋
背骨や骨盤、肋骨や肩甲骨の下部から、腕へとつながっている大きな三角形状の筋肉が広背筋(こうはいきん)で、いわゆる「逆三角形」を形成する筋肉です。上部と下部に分けられ、腕を内側にひねったり腕をうしろに引き寄せる働きをします。上から下に肘を引く動きでは主に上部が、前から後ろに肘を引く動きでは主に下部を使います。
スポーツでは、やり投げや野球のような投球動作、サッカーやラグビーのような腕を使って相手の動きを抑えるコンタクトスポーツをする時に重要な筋肉です。
広背筋は、鍛えるのが難しい筋肉とも言われています。自分では動きが見えない上に、腕の力に頼ってしまったり、力を入れる感覚が分かりにくかったりするためです。詳細は後述します。
脊柱起立筋
脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)は頭から骨盤まで、人間の背中の中心部あたりを、縦に細長く走っている筋肉です。姿勢を維持したり腰を反ったり、身体を横に傾けたりする動作を行います。鍛えることで背中の厚みを作ることができます。
一般的な背筋運動のように、反る運動で鍛えられる筋肉です。一方でとても大きな力を発揮する筋肉なので、重りを使わない背筋運動ではすぐに負荷が足りなくなります。そのため重りを頭に乗せて背筋を行う、ダンベルやバーベルを床から持ち上げるデッドリフトなどが有効な種目です。
スポーツでは、ゴルフのドライバーや野球のバッティング、ハンマー投げなどのように、ボールなどを遠くに飛ばす競技で特に重要な働きをします。またラグビーのスクラムのように、体幹を固定しなければならない動作にも欠かせません。
背中の筋肉を鍛えるメリット
背中の筋肉を鍛えると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
見た目が良くなる
広背筋を鍛えるとボリュームが横に広がります。憧れる男性の多い逆三角形のシルエットを作ることができるのがこの広背筋です。男性の場合は背中にボリュームが出ることで、とても見栄えが良くなり女性は僧帽筋、脊柱起立筋の厚みを作ることでビーナスライン(背中の中心にできる縦線)を浮き上がらせることができます。また、脊柱起立筋の下部に厚みを作ることで、ビーナスのえくぼ(腰の上のくぼみ)を作れます。
男性も女性も美しい背中を作ることができれば、背中が開いた洋服や水着を自信もって着られるでしょう。背中の筋肉を鍛えることで、かっこよさや美しさを磨くことができます。
姿勢が良くなる
背中の筋肉を鍛えると、姿勢が良くなります。反対に、僧帽筋や菱形筋(りょうけいきん)が弱くなると猫背になっていきます。菱形筋とは僧帽筋深部で、肩甲骨の間にある筋肉です。
僧帽筋中部と菱形筋は、肩甲骨を内側に寄せて胸を張るときに働く筋肉ですが、これらの筋肉が弱くなると、肩甲骨が外側に広がって猫背になってしまいます。また、脊柱起立筋が弱まると骨盤が後傾して背骨のS字カーブが崩れ、丸まってしまいます。
このように背中の筋肉が弱まると、肩甲骨が外側に広がる上に背骨が丸まることで、より猫背になるのです。背中の筋肉を鍛えれば、猫背を改善して姿勢を改善できます。
肩こり・腰痛予防

背中を鍛えることは、肩こりと腰痛の予防や改善にも効果的です。僧帽筋のこり、こわばりが肩こりの原因の1つです。デスクワークや勉強で、合っていない椅子やデスクを使っていると、肩甲骨を上げた状態で長時間作業をすることになります。このとき僧帽筋は長時間緊張し続けるため硬くなってしまい、こりやこわばりになってしまいます。さらに日常生活ではあまり肩を大きく動かすことがないため、僧帽筋がストレッチされる機会がありません。僧帽筋を鍛えるときに大きく動かすことで、こりやこわばりの解消につながります。
また脊柱起立筋が弱くなると骨盤が後傾して背中が丸まってしまいます。この状態は背骨のS字カーブが崩れて腰に負担がかかってしまい、腰痛につながりかねません。さらに腰が丸まることで腰周りの筋肉を痛めたり、椎間板に負荷がかかってヘルニアを発症したりなどのリスクがあります。脊柱起立筋を鍛えて、骨盤の位置と背骨のS字カーブを整えることができれば、これらの改善を期待できます。
背中の筋肉が鍛えにくい理由
背中の筋肉を鍛えるのは難しいと言われています。背中の筋肉が鍛えにくい理由は、主に動きが見えないことと、腕の力に頼ってしまうことです。
動きが見えない
胸や腕、肩などのトレーニングは、鏡に写して筋肉の動きを確認しながら行えます。これによりマッスルマインドコネクションが生まれます。マッスルマインドコネクションとは、筋肉と意識を連結させることです。
筋肉を鍛えるときは、鍛えている筋肉の収縮を意識することで、より効果が高まると考えられています。そのため胸や腕、肩のように収縮を意識しやすい筋肉は鍛えやすいのです。しかし背中の筋肉は背部にあるため、トレーニングをしながら筋肉の動きを確認できず、マッスルマインドコネクションが生じにくいのです。
さらに広背筋は鍛えにくいと言われます。広背筋をより鍛えることができるのは、綱のぼりのように肘を引きながら上に登るような動作です。しかし現代で普通に生活していると、こういった動作を行うことはあまりありません。そのため、広背筋を収縮させる感覚があまりわからない人が多く、マッスルマインドコネクションが生まれにくいようです。広背筋を収縮させる感覚をつかむためには、ある程度トレーニング経験を積む必要があります。
腕の力に頼ってしまう

広背筋を鍛える種目では、懸垂やラットプルダウンが主流です。しかし、広背筋を収縮させる感覚がつかめないままで行うと、上腕二頭筋の力に頼ってしまうことがあります。こうなると腕ばかりが鍛えられて、あまり広背筋を鍛えられません。
こういった種目で広背筋に効かせるためには、腕に頼らず、広背筋を使うための正しいフォームと意識が重要です。
おすすめの背中のトレーニング種目
ここでは背中のトレーニング種目のおすすめ3選を紹介します。背中に効かせるためのフォームや意識も解説するのでぜひ実践してみてください。
懸垂
懸垂は広背筋と、広背筋の上部にある小さな筋肉の大円筋などがターゲットです。補助的に上腕二頭筋や三角筋後部(肩)も働きます。初心者には少し難しい種目なため、できない場合は懸垂バーからチューブを垂らして足をかけて補助にしたり、足が届くように台を置いたりして行いましょう。
1.手の幅は肩幅よりやや広めに取り、順手(手の甲が自分側)でバーを握ります。このポジションが辛い人は、幅を狭くして逆手(手のひらが自分側)でも構いません。


2.バーに近づけるように胸を張り、肘を背中側に引いて体を引き上げます。膝は軽く曲げます。肘を腰の斜め後ろに当てるような意識を持つと、広背筋に効きやすくなります。

3.あごとバーが同じくらいの高さまで体を上げ、1秒間キープします。

4.ゆっくりと体を下ろします。

できる回数を3セット行いましょう。
ダンベルベントオーバーローイング
ダンベルベントオーバーローイングは、背中全体に負荷をかけられる種目です。特に僧帽筋を鍛えられる種目で、広背筋や菱形筋、三角筋後部にも効きます。
1.ダンベルを持ち、脚を肩幅にして両膝を軽く曲げ、背筋を伸ばしたまま上体を45度前に倒します。

2.スタートポジションを維持したまま、肩甲骨を寄せるイメージでダンベルを持ち上げます。

3.同じ動線でゆっくりとダンベルを下ろしていきます。
10回を3セット行いましょう。
ダンベルデッドリフト
「筋トレのBIG3」の1つであるデッドリフトのダンベル版です。主に脊柱起立筋が鍛えられます。ほかにも、大腿四頭筋(太ももの前)、ハムストリングス(太ももの後ろ)、大殿筋(お尻)にも効かせられる種目です。
1.両手にダンベルを持ち、足を肩幅に広げます。
2.背中を丸めることなく直線になるようにキープします。視線は真っすぐ正面に。

3.腹圧をかけ(お腹にしっかりと力を入れ)、体がまっすぐになるまでダンベルを持ち上げます。

4.トップでは胸を張って肘を引き、背中の筋肉の収縮を意識します。
5.腹圧を抜かないように、元の位置に戻します。
10回を3セット行いましょう。
まとめ
背中の筋肉を鍛えると、たくましい逆三角形の背中や、ビーナスラインの美しい背中に近づくといった見た目の良さだけではなく、姿勢が良くなる、肩こり・腰痛予防などのメリットがあります。しかし背中の筋肉は直接見えないため、うまく鍛えるためにはコツが必要です。
自分では難しい場合、スポーツジムに通ってインストラクターの指導を受けると巧く鍛えられます。この機会にお近くの スポーツクラブNASの店舗 へお問い合わせください。
関連記事Related Articles

肩こり・首コリに効く!こわばった僧帽筋をほぐすストレッチを紹介
肩こりや首コリがひどくて「首が回らない」「腕が上がらない」といった悩みは、中高年だけでなく若い世代にも共通しています。その多くは、長時間のス...
フィットネス
体幹トレーニングとは? その効果とおすすめエクササイズ5選を紹介
「体幹トレーニング」という言葉は聞いたことがあっても、明確なイメージを持っている人はあまり多くないのではないでしょうか。この記事では体幹の定...
フィットネス
お尻の筋肉はとても重要!鍛えるメリットを徹底解説
お尻の筋肉は日常生活での動作はもちろん、見た目の美しさやスポーツのパフォーマンスにも重要な部位です。お尻の筋肉を鍛えることで、たくさんのメリ...
フィットネス
ジムに毎日通ってもよい?毎日通うメリット・デメリットも解説
健康やボディメイクのため、たまによりも毎日ジムに通う方が効果的だと考える人もいます。毎日ジムに通うことにはメリットがある一方で、いくつか注意...
フィットネス
肩甲骨周りが痛い……その原因と改善するストレッチ方法を解説
肩凝りなど肩甲骨周りの痛みに悩んでいる方は多くいます。特にデスクワークや運動不足は肩凝りにつながりやすく、現代病の一つともいえるでしょう。パ...
フィットネス
引き締まった美尻を手に入れる! ヒップアップのためのエクササイズ3選
女性にとっても男性にとっても、美しいヒップラインはいつの時代でも憧れの的です。キュッと引き締まった立体的で弾力の感じられるヒップは、理想的と...
フィットネス
筋肉痛のときの筋トレはあり? 筋肉痛を早く治す方法と予防法を解説
筋トレをした次の日に襲ってくる筋肉痛は、心地よさを感じる軽いものから手足を動かすのが嫌になるほど辛いものまで、痛みの強さはさまざまです。筋肉...
フィットネス
最適な時間帯はいつ? 朝・夕方・夜に筋トレするメリットとデメリット
筋トレを始めようと思ったとき、「どの時間帯にやるのが正解なんだろう」と悩んでいる人も多いでしょう。せっかく始めるなら、最も効率の良い時間帯に...
フィットネス